「ダイニングテーブルって、だいたいどれも同じような高さじゃないの?」
家づくりを始める前は、私もそんなふうに思っていました。
でも実際に家具屋さんで座ってみると、たった2cmの違いなのに、座り心地や印象がまるで違うことにびっくり。
先日、我が家がよくお世話になっているナチュラル系の家具屋さんに行ってきました。
これで4回目の訪問。今回は、注文済のダイニングテーブルの「高さ」を68cmか70cm、どちらにするか最終決定するための来店でした。
そして、実はこの“たった2cm”の違いに、私たち夫婦の身長差や暮らし方の違いがかなり影響していたのです。
この記事では、私たちがダイニングテーブルの高さをどうやって選んだのか、迷ったポイントや決め手になったこと、そして店員さんから教えてもらった“文化によるテーブルの違い”まで、リアルな体験をお届けします。
- ダイニングテーブルの高さ68cmと70cmの具体的な違いと座り心地の比較
- 夫婦の身長差(182cmと160cm)による感じ方の違い
- テーブルの高さを選ぶときの用途別の考え方(食事/作業/くつろぎ)
- 実際に座って体感したうえでの決断プロセス
- 家具屋さんで教わった、国や文化によるテーブル高さの違い
- テーブルの高さが暮らしにどう影響するかの実体験
- 「たった2cm」の違いでも生活の快適さが変わることの気づき
家具選びで「高さ」を意識したきっかけ

我が家は現在、コの字型の平屋を建築中です。
キッチンのすぐ横にダイニングテーブル(ナガノインテリアのDT671)を置く予定で、食事はもちろん、PC作業や読書など、一日の中でいちばん長く過ごす場所になる予定のスペース。
ダイニングには、すでにお気に入りのキタニの椅子2脚と2人掛けのベンチを注文済み。
あとはテーブルの高さを決めるだけ…だったのですが、「作業しやすい高さって何cm?」「リラックス感も大事にしたい…」と、意外と迷ってしまって。
夫(182cm)と私(160cm)では、座ったときの感覚も違います。
どちらか一方の感覚だけで決めると、暮らし始めてから「なんかしっくりこないな…」なんてこともあるかもしれない。
そんな思いもあって、「実際に座って比べて、体感してから決めよう!」と、今回の来店に至りました。
ちなみにわが家の一番の推し家具 キタニの椅子🪑についてはこちらをご覧ください👇

68cm vs 70cmの印象と違い
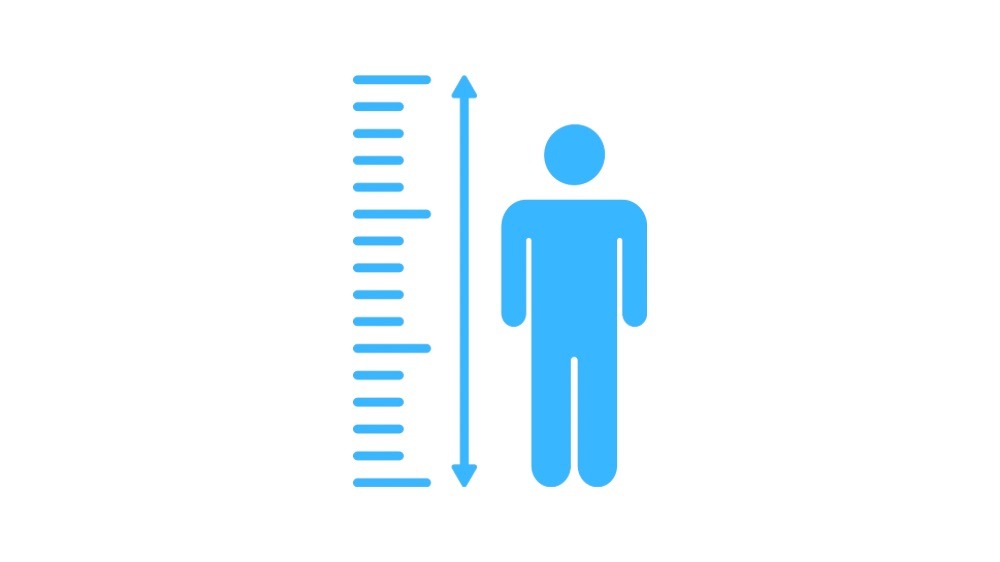
家具屋さんで用意されていたテーブルは、高さが68cmと70cmの2パターン。
「たった2cmしか違わないのに、そんなに変わるの?」と思いつつ、実際に座ってみると…びっくり。印象がまるで違うんです。
68cmの方は、少し低めで落ち着く感じ。
カフェのようなゆったりした雰囲気で、「お茶したり本を読むにはいいな〜」と感じました。
ただ、ごはんを食べたり作業をしたりするには、ちょっと低いかも?というのが正直な感想。
一方、70cmの方は自然と背筋が伸びる感覚があり、食事やPC作業にはぴったり。
私(160cm)は「こっちの方が姿勢が楽!」と感じたのですが、夫(182cm)からはこんな感想が。
 夫
夫70cmは普通かな。68cmはちょっと低いって感じた。
なるほど。
身長が高い人も、一般人(私)と同じような意見でした。
身長高い人の方が“低さ”には敏感なのかも?と思ったけど、夫の意見からではよくわかりませんでした。
使うシーンを思い浮かべながら、「高さって、たった2cmでも割と違うんだな…」と実感しました。
ちなみに家が建ってやりたいことリストの中に、
キタニの椅子に座って、ダイニングテーブルでブログを書くことがランクインしています。
良かったらこちらの記事も見てみてください👇


夫婦の身長差と使い方、それぞれの希望と決断の理由


改めて、我が家の身長バランスは夫が182cm、私が160cm。
同じテーブルに座っていても、感じ方はけっこう違うようです。
夫は「70cmは普通」「68cmはちょっと低い」と話していて、高さに強いこだわりはなさそうでした。
一方の私は、ダイニングテーブルで食事以外にもPC作業や読書をするつもりだったので、姿勢が保ちやすい70cmを推したい気持ちが強かったです。
しかも、実際に座ってみると70cmの方が自然と背筋が伸びる感覚があって、「作業のしやすさ」で選ぶならこっちだなと確信。
最終的には



じゃあ70cmでいいよ。俺もそっちのがいい。
と、夫もすんなり納得。
(適当に聞こえたのは私だけ?笑)
我が家のテーブル高さは70cmに決定しました✨
店員さんから聞いた、文化によるテーブル高さの違い


今回の訪問では、店員さんとの何気ない会話の中で、興味深い話を聞くことができました。
それが「テーブルの高さは、文化によって違うんですよ」というお話。
たとえば、イタリアではダイニングテーブルの高さがもっと高いことが多いそう。 理由は、食事前にお祈りする文化があり、子どもたちも自然と背筋が伸びやすいような高さに作られているから。 また、ナイフとフォークを使う食文化なので、お箸文化の日本と比べて高めでも問題がないとのことでした。
すごく興味深かったので、あとで調べてみると「祈りの文化があるからテーブルが高い」というのは一つの見方ではあるものの、必ずしもそれが主な理由ではないようです! ヨーロッパでは、体格が大きく、椅子の座面も高めに設計されていることが多く、その結果としてテーブルの高さも自然と高くなるという背景があるようです。 また、ナイフとフォークを使う文化では、背筋を伸ばして椅子に深く腰かけて食事をするため、高さがあっても違和感がないという点もポイントのようです。
逆に、日本はお箸での食事が基本で、鍋を囲んだり、テーブルを“共有”する文化も根付いているので、少し低めの68cm前後が落ち着くという人も多いのだとか。
さらに、店員さんいわく「韓国や中国では結構低いテーブルで食べる文化もあるみたいですよ」とのことで、“どんな姿勢で、どんな食事をするか”によって、自然とテーブルの高さも変わってくるのだと実感しました。
またここも調べてみたので補足すると、韓国では伝統的にオンドル(床暖房)のある部屋で、低いテーブルを囲んで床に座って食事をする文化がありました。現代ではダイニングテーブルが主流になってきていますが、地方や家庭によっては床座りスタイルも残っています。
一方、中国では古くから椅子とテーブルを使う文化が根付いていて、床に座るスタイルはあまり一般的ではないそうです。そのため、中国ではテーブルの高さも比較的高めで、ナイフやフォークを使う西洋式の文化と近いスタイルが多いという特徴があるそうです。
今回店員さんのお話を聞いて、国や地域によってテーブルや家具の高さに違いがあることを知れてすごくおもしろかったです。家具ってただの道具だけじゃなくて、その国の暮らしや文化を映すものなんだなぁ、と改めて実感しました😲
まとめ:数字だけではなく“暮らし”から選ぶ高さの話


家具選びって、見た目や素材、価格に目がいきがちだけど、“高さ”も暮らし心地を左右する大切な要素だと、今回改めて感じました。
実際に座ってみてたった2cmの違いでも、座ったときの印象がかなり変わりました。
身長や体格の問題だけでなく、そのダイニングテーブルで「どう過ごしたいか」「何を優先するか」によって高さを選ぶことが大切です。
我が家の場合は、
- 食事+作業をする場として → 70cmがちょうどよかった
- 身長差がある夫婦でも → 体感的に違和感はなかった
- 文化的な背景も含めて → 自分たちの感覚に合った選択ができた
家具屋さんで実際に座ってみたり、店員さんと会話したことで、「この高さで過ごす未来の自分たち」がはっきり想像できたのが一番の収穫でした。
これからダイニングテーブルを選ぶ方には、高さという数字だけを見て決めるのではなく、
「自分たちはここでどんなふうに過ごしたい?」
と一度立ち止まって考えてみることをおすすめします💡
ここまで記事を読んでくださりありがとうございました!
この記事があなたのお役に立てれば嬉しいです😊
ほややん

コメント